農業TOP EYE

「農業TOP EYE」は、経営・農業機械・人材教育・販売などをテーマに、多彩な業界のキーパーソンにインタビューし、農業経営に役立つ情報をお届けするコーナーです。
第2回は、高品質な水稲の種もみ生産で全国的に名高い、富山県のとなみ野農業協同組合 代表理事組合長 佐野日出勇氏にお話を伺いました。
何十年先の未来を見据え、
活力にあふれる産地づくり、
そして農業による地域活性化をめざします。
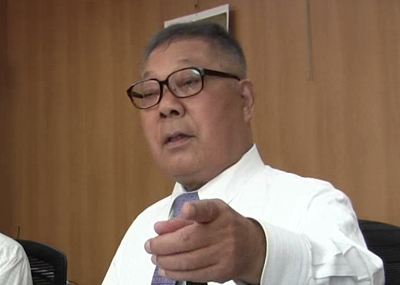
となみ野農業協同組合
代表理事組合長
佐野 日出勇 氏
取材日:2017年10月11日
まず、となみ野農業協同組合が考える農業の基本戦略について
お聞かせください。
佐野組合長大きく分けて3 つの基本戦略があります。
一つ目は「後継者、担い手の育成」です。生産者の減少や高齢化が進む中、いま問われているのは、"いかに若い世代の担い手や優秀なオペレーターを増やしていくか"。そのために、行政機関と協力し合って優秀な担い手を育成していきます。
二つ目は「複合経営の拡大による儲かる農業への転身」。儲かる農業でなければ、若い人の農業参入にはつながりません。そこで当農協では、9 年前から水稲の裏作として収益性の高い「たまねぎ」の作付を開始し、面積を拡大してきました。現在では販売額が水稲・大豆・大麦に次ぐまでに成長しています。数年後にはこのたまねぎが表作となるように、さらなる生産量拡大を推進中です。

いま抱えている「農業の課題」は
なんですか。
佐野組合長いかに担い手を確保し、活力ある産地を構築していくかが大きな課題で、先ほど申し上げた一つ目の基本戦略の背景には、こうした問題があります。農業というビジネスの環境をきちんと整備して、若い担い手が集まるようにしないと地域全体の経済活動が滞り、産地が、そして村や町が衰退してしまう。このままなにも手を打たないと、なに年か先にはそれが現実化してしまうような段階にあるのではないかと思います。
だから、このまま単純に農業をやっているだけではだめなんです。いまの若い人たちがなにを考えていて、どうしたら農業を好きになってくれるのか。そうした若い人たちの取り込みを真剣に考えないと、産地は弱体化してしまい、地域の活性化も望めません。これから数年後はもちろん、10 年先、20 年先、そして100 年先さえも視野に入れた農業と地域について、私たち農協は考えていかなければならないんです。
「担い手の確保」には、
なにが重要だと思われますか。
佐野組合長まず、農業という経済の基盤を再整備することが大事です。そのためには「儲かる農業」であることが問われます。農業で収益を上げられるようにしないと、生産者の皆さんの収入が安定しませんからね。 それから、一般企業と同等の社会保障・福利厚生・労働環境を整備することも重要です。いまの若い人たちは、きちんと休みを取りたいという要望が強いので、そんな要望にもしっかり応えたい。例えば、農作業を早朝に頑張って終わらせてしまえば、あとは1 日休みにしてしまうとか、法人化を進めて休みを取りやすくするなど、若い人たちの目線で考えた方策が必要ですね。当たり前のことですが、これからの農業は、若い人材の存在なくして成り立たないし、産地の活性化はあり得ないんです。
優秀な担い手を育成するために
「研修センター」を
立ち上げるそうですね。
佐野組合長栽培・防除技術といった営農関係の講習と農業機械の修理・整備ができる担い手の育成を図るべく、行政機関と共同で「研修センター」の開設を準備しているところです。
作業効率や品質を上げて収益を高め、「儲かる農業」を実現するためには、圃場の大区画化と大型機械の活用が必要です。そのキーになるのは「優秀なオペレーター」という担い手の存在だと考えているんです。なぜかと言うと、優秀なオペレーターは、大型機械の取り扱いやメンテナンスだけでなく、周りを引っ張っていく力を持っている。なにをさせても上手なんですね。優秀なオペレーターが数人確保できれば、その営農組織は円滑に運営できる。だから、そんなオペレーターを育成する研修センターのような機関は、産地にとって絶対に必要なんです。

富山と言えば高品質な種もみのイメージが
あります。
その水稲作について
お聞かせください。
佐野組合長当農協管内は排水性の良い沖積砂壌土地帯で豊富な灌漑水に恵まれ、昼夜の寒暖差も大きいことから、品質の高い米の生産に適した産地なんです。水稲作の歴史は160年以上にも及び、その品質の高さは全国から評価をいただいています。おかげさまで種もみの県外向け受託生産量も、40種以上あるその品種数も日本一です。これまで積み上げてきた信頼と実績により、米価低迷の環境下でも安定した販売を展開しています。
そんな中、今年からお米の販売体制で
大きな変革を
実施されたそうですね。

全量を買い取ることで、売れ残りや米価の急激な変動というリスクを抱えながらも、この販売体制に踏み切ったことにより、生産者の皆さんに対して農協の存在感を大きくアピールすることができたと自負しています。
住友化学の品種『つくばSD2号』を
作付いただいております。
導入された背景についてお聞かせください。
佐野組合長2018年からコメの生産調整が廃止され、米価の変動が不透明な時期を迎えるにあたり、「売れるコメ」の生産が問われています。そんな環境のなか、ここ数年の間に、一般消費用米よりも安価で、冷めても食味の劣化が少ない業務用米のニーズが高まってきました。
そんなとき、住友化学の『つくばSD2号』をご紹介いただき、2年の試験を経て今年から本格的に作付を開始しました。まだ正確なデータが出ていませんが、今年は日照不足などの関係で従来のコシヒカリの収量が伸び悩んだなか、『つくばSD2号』は従来のコシヒカリよりも多収で、倒伏が少なかったという報告を受けています。今年は189ha作付しましたが、知見を積み上げながら栽培技術を確立させて、今後はさらに面積を拡大していきたいですね。
水稲をはじめとする農作業の省力化では、
どのようなことに取り組まれていますか。
佐野組合長まだ取り組みはじめたばかりですが、ドローンの活用を積極的に推進しています。ドローンは上空から水田を動画撮影することで、どこにどんな雑草が生えているか、どこの稲が肥料不足の状態かなど、一目瞭然でチェックできます。採種圃場の場合は、こぼれ籾による異品種や雑草などのチェック・抜き取りのために、シーズン中に3~4回ほど圃場に入らなければなりませんが、ドローンを活用すれば30分ほどで済んでしまいます。
こうした技術革新を背景として、昨年、ソリューション事業部という部署を立ち上げ、ドローンの免許取得サポートなどを核とした活動を展開中です。
販売額が水稲、大豆、大麦に次ぐまでに
成長した「たまねぎ」について
教えてください。

作付初年度は8ha からスタートしましたが、10年目の今年は200ha まで面積が拡大しました。これだけの短期間に単協ベースで、ひとつの作物を基幹作物に成長させた例は、非常にまれなケースなのではないでしょうか。
今後の取り組みついては、
どのようにお考えでしょうか。


起工式が行われていた
これからは米だけで農業経営の成長を実現するのは難しい。だから、たまねぎの生産量拡大に産地をあげて注力していきます。たまねぎは収益性が高いので、複合経営でたまねぎを手がけている組織は、すごく活発で意欲的なんです。管内の生産者のみなさんは、肌身でそれを感じ、たまねぎの作付に魅力を感じている人が多い。
そのためにも一日も早く、冒頭に申し上げたオペレーターの養成や大区画化への基盤整備に取り組み、若い担い手が現場を支える活力にあふれた産地づくりをめざしたい。そして、観光資源と一体となった農業で、となみ野の地域活性化に貢献していきたい。
私はこの産地を代表する農協の経営者として、強く強く、そして着実にそのビジョンを推し進めることに全精力を注いでまいります。